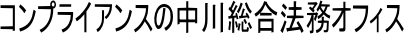1.心理的安全性 psychological safety の分析概念について
この概念の有用性を述べている第一人者は、「恐れのない組織(The Fearless Organization)」の著者 エイミー・C・エドモンドソン Amy C. Edmondson ハーバード・ビジネススクール教授 であろうか。
曰く、組織の中で自分の考えや気持ちを誰に対してでも安心して発言できる状態 では、生産性が高いのであろう。Googleが2016年に「生産性が高いチームは心理的安全性が高い」との研究結果を発表していることから、説得力が出てきたのであろう。
著書の中での理論と実践法などが広く出回るようになってきている。
「チームにおいて、メンバーが自分の考えや感情をオープンに表現し、リスクを恐れずに行動できると信じられている状態」では、メンバーは安心して意見を言い合うことができ、失敗を恐れずにチャレンジすることができ、イノベーションや生産性の向上につながる。
心理的安全性を高めるためには、、「メンバー同士の信頼関係と互いを尊重している状態」が不可欠であり、さらに重要なのが「寛容さ」で、メンバー同士が互いの失敗や間違いを許容している状態が大切である。
もっともこのような状態のチームを作っていくには、いわゆるコンプライアンス環境が不可欠で、正しいPMリーダーシップ論等を採用して、メンバー同士が信頼し合い、敬意を持って、寛容であるような文化や空気を醸成する必要がある。
2.心理的安全性とコンプライアンスとの関係
この考え方は、当方のような700回以上のコンプライアンス研修や講演講師を務めたものには、すぐに「内部通報」との関係で、組織の法令や倫理違反を上司や相談窓口に言うことのできる組織は、コンプライアンス経営環境があると毎回言っているので、コンプライアンスマネジメントには好ましい印象がある。
しかし、何を言っても恐れのない、自己の発言に全く不安のない組織などはあるのであろうか。内部通報における自己と組織の倫理の衝突や組織の地位とカネに絡んだ打算を強く吹き飛ばせるほどの力のある分析概念なのであろうか。
理論がアカデミックに過ぎない感がどうしても否めない。
或いは理想論に過ぎないと言ってもいいかもしれない。
しかし、コンプライアンスマネジメント環境に重要な示唆を与えていることは間違いなかろう。
「見てみないふりをする」
「言うだけ損」
「藪蛇」
「火の粉が自分に降りかかる」
これらの考えのある組織が、コンプライアンス上は駄目であることは明らかだからである。
3.心理的安全性のある組織がコンプライアンスにとって理想
やはり現時点では、グーグルの例が、さらにコンプライアンスマネジメントまでの論理展開は飛躍し過ぎであろう。
しかし、内外で著書や論考が今後も出てくるであろう。
引き続き、これをコンプライアンスマネジメントに活かす方法をこれら論文などを参考にしながら進めていきたい。
中川総合法務オフィスでは、コンプライアンス関連のコンサルティングや研修では、引き続き、不祥事が起きない組織のリスク管理と企業倫理の向上に最も重点において実施し、心理的安全性の向上もそれに付加する形をとる。
4.組織風土改善に効果的な心理的安全性事例ワーク「コンプライアンス研修」のおすすめ
管理職研修で実証済の、人気のある中川総合法務オフィスの企画書をいますぐ請求する。